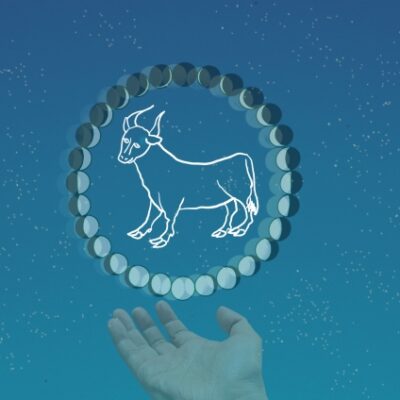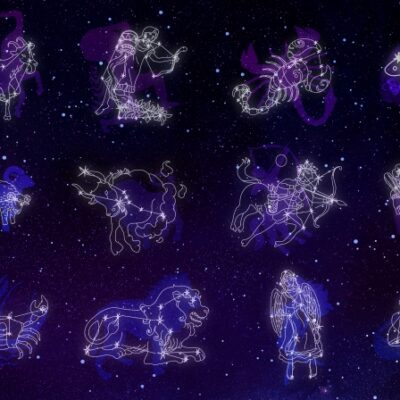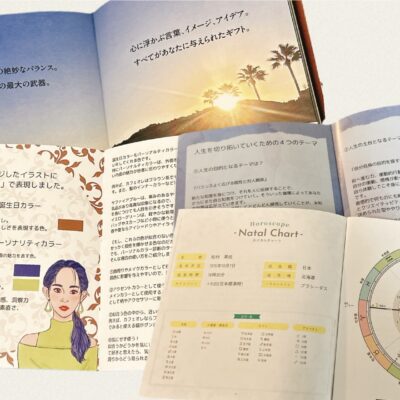私は、とかく小さい頃から苦手なこと、嫌なことが多かったように思う。
朝起きて、同じ毎日の繰り返しが本当に苦痛で。
園児の頃から、お遊戯会の踊りとか運動会の練習とか、まったく自分にとって「興味のないこと」をやる、「必要性を感じないこと」は、ただただ苦痛でしかなく。
また厄介なことに、口数が少なかったのであまり言葉での自己主張をしない代わりに、微動だにせず「練習をしない」という頑固なまでの反抗的態度。
ペアのお友達が毎回困って泣いていても、自分の意思は固く…。
それでも、本番はきっちり踊り切るという…笑
今思えば、周りにとってとても扱いにくい、面倒な子だったと思います。
とはいえ、子供の頃は、そう、本能のままにやりたい・やりたくないを体現していたように思う。
成長するにつれ、周りに合わせることも覚えたら、強制的に全員が同じことをやらなきゃいけない環境はとにかく、しんどかった。
高校生くらいになると、科目の選択や部活の種類も増え、バイトができたりとさまざまな場面で「自分の意思で選択できる」環境になり、のびのびできるようになった。
大学も授業は選べるし、自分で時間割を構成できる。それは私にとってすごくやりやすい環境でした。1年の頃から、どうにか週休3日になるようにうまく組み合わせ、学校に行く日数を減らしました。
今思えば、無意識に集団の中に身を置く時間を少しでも減らしていたんだと思います。(HSPだな)
社会人になって、どんな仕事も興味があることをやっていましたが、組織で働くこと自体は苦手でしんどいことが多かった。
だけど、そのときの自分が生きていくために「必要なこと」であり、カラーで独立するうえで「必要な学び・経験」と思えたから、嫌な環境でも頑張れたんだろうと思っています。
「やりたいこと」は自然と動けるけど、「やらなきゃいけないこと」だとテンションが上がらない。
だから、「必要だからやる」に切り替えると、自分自身の中で受け止め方が変わってきます。
どっちにしろやらなきゃいけないなら、少しでも気分が軽く、足取りも軽くできるほうがやっていて気持ちがいい。
だから、楽しむ工夫をその中に見つけてやる。
事務処理だったら、いかに最短時間でできるかと工夫できる箇所を見つけ、無駄を省くゲームをやる感覚で。
掃除だったら、1箇所決めて徹底的に綺麗にするとか。
タスク化してチェックリストにチェックが埋めていくことで達成感を味わうとか。
わたしは、そんなふうに工夫しながらやっていました。
「嫌なこと」で「必要ないこと」なら、やらなくていい。
「嫌なこと」で「やる必要があること」は、イヤイヤやっていたら「嫌な気持ち」のエネルギーが乗っかってしまう。
だったら少しでも「楽しい気持ち」のエネルギーを乗っけたほうが絶対にうまくいく。